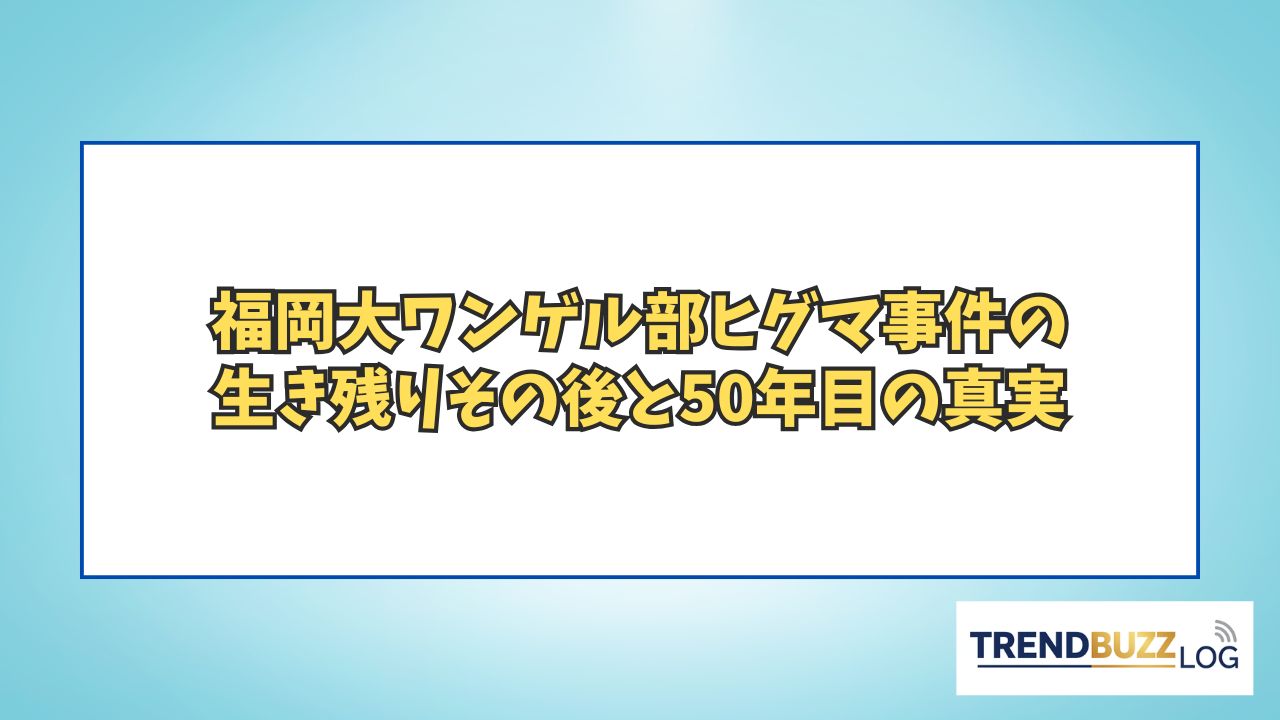1970年7月、北海道の日高山脈で発生した「福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件」は、日本の獣害史上最悪の悲劇の一つとして知られています。
将来有望な若者3名の命が奪われたこの事件には、奇跡的に生還した2名の部員がいました。
彼らはその後、どのような人生を歩んだのでしょうか。
本記事では、事件の生き残りである2名のその後と、50年の時を経て語られた真実、そして彼らが残した教訓について詳しく解説します。
当時の状況や背景を知ることで、私たちが自然とどう向き合うべきかを考えるきっかけになれば幸いです。
福岡大ワンゲル部事件の生き残り2名はその後どうなったのか?
事件から半世紀以上が経過した今も、多くの人々の記憶に残るこの惨劇。
生き残った2名の部員がその後どのような人生を送ったのか、公に語られる機会は極めて稀でした。
ここでは、生存者のプロフィールと、長い沈黙を破って語られた言葉について解説します。
生存者であるサブリーダーと1年生部員のプロフィール
当時、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会のパーティーは5名で構成されていました。
そのうち、生還を果たしたのはサブリーダーを務めていた当時22歳の学生と、入学したばかりで当時19歳だった1年生部員の2名です。
サブリーダーは法学部の3年生で、リーダーを補佐し、パーティー全体を統率する立場にありました。
一方、1年生部員はまだ登山経験も浅く、上級生についていくことで精一杯の状況だったと推測されます。
2人は襲撃の混乱の中、リーダーの指示や状況判断により、救助要請のために下山を試みたり、ヒグマの追跡から逃れることに成功しました。
彼らは五の沢の砂防ダム工事現場までたどり着き、そこで保護され、九死に一生を得ることとなります。
事件から50年後の告白「記憶を封印してきた」
事件後、生き残った2人がメディアの前で詳細を語ることはほとんどありませんでした。
しかし、事件から50年という節目を迎えた2020年、当時のサブリーダーが週刊文春の取材に応じ、重い口を開きました。
彼は「あのときのことは自分の中で、この50年間、封印してきました」と語っています。
そして、「今でも何かの拍子に思い出すと眠れなくなる」と、半世紀経っても消えることのない深いトラウマを抱えていることを明かしました。
目の前で仲間を失い、自身も死の恐怖に直面した経験は、言葉では言い表せないほどの心の傷として残り続けていたのです。
この告白は、獣害事件が被害者の肉体だけでなく、精神にも永続的な苦しみを与えることを改めて世に知らしめました。
生き残った2人は現在も登山を続けているのか?
生き残った2人がその後も登山を続けているかどうかについては、明確な公式情報はありません。
しかし、前述の「記憶を封印してきた」「思い出すと眠れなくなる」という言葉からは、事件が彼らの人生にどれほど大きな影を落としたかが想像できます。
山への情熱を持って入部したワンダーフォーゲル部でしたが、あの惨劇を境に、以前と同じ気持ちで山に向かうことは困難だったのではないでしょうか。
彼らは事件後、それぞれの人生を歩み、社会人として生活を送ってきました。
静かに日々を過ごすことが、彼らにとっての精一杯の心の守り方だったのかもしれません。
なぜ3人が犠牲に?福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件の全貌
なぜ、これほどまでに悲惨な事件が起きてしまったのでしょうか。
事件の経過を辿ると、ヒグマの執拗な追跡と、極限状態での学生たちの必死の抵抗が浮かび上がってきます。
ここでは、3日間にわたる襲撃のタイムラインと、被害の凄惨な実態について解説します。
1970年7月の日高山脈で起きた3日間の惨劇タイムライン
事件は1970年7月25日から27日にかけて、日高山脈のカムイエクウチカウシ山で発生しました。
最初の接触は25日の夕方、九ノ沢カールでテントを設営した後に起こります。
ヒグマが現れ、テントの外にあったザック(リュック)を漁り始めました。
学生たちは音を出してヒグマを追い払い、ザックを取り返しましたが、これが悲劇の引き金となった可能性があります。
その夜、ヒグマは再び現れ、テントに穴を開けるなどの行動を見せました。
翌26日の早朝、ヒグマはテントを倒し、執拗に攻撃を仕掛けてきました。
パーティーは移動を決断しますが、ヒグマは彼らを追跡し続け、夕方には1年生部員1名が襲われ、行方不明となります。
さらに27日の朝、濃霧の中を下山しようとした残りのメンバーも襲撃され、リーダーと3年生部員の計3名が命を落としました。
被害者の遺体の状況と判明した死因
事件後に発見された3名の遺体は、目を覆いたくなるような惨状でした。
衣服は引き裂かれ、体には無数の爪痕や噛み傷が残されており、一部は食害を受けた痕跡もありました。
検死の結果、死因は「頸椎骨折」および「頸動脈切断による失血死」と判明しています。
これは、ヒグマが一撃で致命傷を与えるほどの圧倒的な力を持っていたことを示しています。
彼らは逃げる最中、背後から襲われ、なす術もなく命を奪われてしまったのです。
この事実は、野生動物であるヒグマがいかに恐ろしい殺傷能力を持っているかを如実に物語っています。
加害グマの正体と射殺後の胃の内容物
3人の命を奪ったヒグマは、事件発生から数日後の7月29日、捜索隊のハンターによって射殺されました。
このヒグマは4歳のメスで、体長は約1.5メートルから2メートル程度だったとされています(剥製作成時に縮小したため記録に幅があります)。
通常、人間を襲うクマは老齢や手負いで狩りができない個体が多いと言われますが、この個体は若く健康でした。
射殺後の解剖で胃の内容物を調べたところ、驚くべき事実が判明します。
胃の中からは、人間の肉片などはほとんど検出されませんでした。
つまり、このヒグマは「捕食(食べる)」ことを主目的として人間を襲ったわけではなかった可能性が高いのです。
自分の獲物(ザック)を奪われたことへの執着や、排除行動として人間を攻撃したと考えられています。
死の直前まで書き残された「興梠メモ」の内容とは?
この事件を語る上で欠かせないのが、犠牲者の一人である興梠盛男さんが残したメモの存在です。
極限の恐怖の中で綴られたその内容は、読む者の胸を締め付けます。
ここでは、通称「興梠メモ」と呼ばれる記録の詳細について解説します。
「博多に帰りたい」震える文字で綴られた絶望の記録
興梠さんは仲間とはぐれた後、テントの中に身を潜めながら、手帳に鉛筆で状況を書き記していました。
その文字は恐怖で震え、乱れており、当時の緊迫した状況を生々しく伝えています。
メモには「ああ、早く博多に帰りたい」という、故郷への切実な思いが綴られていました。
まだ19歳という若さで、見知らぬ北の大地で孤独と恐怖に耐えながら、家族や故郷を思った彼の心中を察すると、言葉になりません。
この一文は、事件の悲劇性を象徴する言葉として、多くの人々の涙を誘いました。
ノートに記されていたヒグマの行動と最後の言葉
メモには、自身の心境だけでなく、ヒグマの具体的な行動も記録されていました。
「5m上に、やはりクマがいた。とても出られないので、このままテントの中にいる」
「また、クマが出そうな予感がするので、またシュラフにもぐり込む」
テントのすぐ外にヒグマが居座り、脱出の機会を完全に封じられていた状況が分かります。
彼は冷静さを保とうと努めながら、いつ助けが来るのか、仲間はどうなったのかを案じ続けていました。
メモは途中で判読不能な文字になり、唐突に終わっています。
これが彼が残した最後のメッセージとなり、その後、彼は帰らぬ人となりました。
遺品となったメモは現在どこにあるのか?
興梠さんが命がけで残したこのメモは、貴重な遺品として回収されました。
現在は、北海道中札内村にある「日高山脈山岳センター」に資料として展示・保管されているという情報があります(※展示状況は変更される可能性があります)。
また、同センターには加害グマの剥製も展示されており、事件の恐ろしさを今に伝えています。
このメモは、単なる遺品というだけでなく、ヒグマ襲撃時のリアルな記録として、獣害対策や研究においても重要な資料となっています。
彼の死を無駄にしないためにも、この記録は後世に語り継がれるべきものです。
なぜ彼らはすぐに下山しなかったのか?批判と当時の常識
事件後、「なぜもっと早く下山しなかったのか」という疑問や批判の声が上がりました。
しかし、現代の常識で当時の判断を断罪することはできません。
ここでは、彼らが下山できなかった背景と、当時の状況について考察します。
ネット(なんJ)などで議論される「荷物を取り返した」判断
インターネット上の掲示板(なんJなど)では、たびたびこの事件が話題になり、「荷物を取り返したのが致命的だった」と指摘されます。
確かに、一度ヒグマに奪われたザックを取り返したことで、ヒグマは「自分の獲物を人間に奪われた」と認識し、執着心を強めたと分析されています。
しかし、ザックの中には現金や身分証明書などの貴重品が入っていました。
学生という立場で、遠征費を工面して参加していた彼らにとって、全財産とも言える荷物を山中に放棄するという決断は、容易ではなかったはずです。
「取り返してはいけない」という知識がなければ、本能的に大切な物を取り戻そうとするのは、人間として無理からぬ行動だったと言えます。
当時のヒグマに対する知識不足と正常性バイアス
1970年当時、ヒグマの生態や遭遇時の対処法に関する知識は、現在ほど一般に浸透していませんでした。
「ラジオを鳴らせば逃げる」「火を焚けば寄ってこない」といった、現在では効果が疑問視される対策が信じられていた時代です。
彼らもまた、そうした断片的な知識を頼りに対応していました。
また、「まさか自分たちが死ぬことはないだろう」という正常性バイアスも働いていたと考えられます。
最初の遭遇時に興味本位で写真を撮っていたことからも、当初は危機感が薄かったことがうかがえます。
ヒグマがこれほど執拗に人間を追跡し、殺害するという事実は、当時の彼らの想像を遥かに超えていたのです。
北海学園大学パーティーとの遭遇と運命の分かれ道
実は、福岡大学のパーティーが襲われる直前、同じ山域で北海学園大学のパーティーもヒグマに遭遇していました。
彼らも荷物を奪われていましたが、迅速に下山を選択し、難を逃れています。
福岡大の生き残り2名が救助要請に向かった際、下山途中の北海学園大パーティーと遭遇しています。
この時、北海学園大側は一緒に下山することを勧めましたが、福岡大の2人は「仲間を残しては行けない」と山に戻ってしまいました。
この判断が、結果的に運命を分けることになります。
仲間を見捨てられないという強い責任感と結束力が、皮肉にも最悪の結果を招いてしまったのです。
福岡大学ワンダーフォーゲル部の現在と事件の教訓
悲劇的な事件から半世紀以上が経ちましたが、福岡大学ワンダーフォーゲル部はその名を残しています。
事件は組織にどのような影響を与え、どのような教訓を残したのでしょうか。
同好会から部へ昇格?現在の活動状況について
事件当時、彼らは「同好会」というステータスでしたが、その後「部」へと昇格を果たしました。
現在も「福岡大学ワンダーフォーゲル部」として活動を継続しており、多くの学生が所属しています。
彼らは登山だけでなく、沢登りやキャンプなど幅広い活動を行っています。
過去の悲劇を教訓とし、安全対策には人一倍力を入れていることでしょう。
事件をタブー視して廃部にするのではなく、その精神を受け継ぎ、活動を続けていることは、亡くなった部員たちへの一つの供養とも言えるかもしれません。
八ノ沢カールに設置された慰霊碑と追悼
事件の現場となった日高山脈の八ノ沢カールには、3人の若者を追悼する慰霊のプレートが設置されています。
「高山に眠れる御霊安かれと挽歌も悲し八の沢」
岩にはめ込まれたこのプレートは、訪れる登山者たちに事件の記憶を静かに伝えています。
また、関係者やOBによって定期的な慰霊登山や追悼行事が行われてきました。
この場所は、単なる事故現場ではなく、自然の厳しさと命の尊さを再確認するための聖地となっています。
この事件が日本のクマ対策に与えた大きな影響
福岡大ワンゲル部事件は、日本の獣害対策における大きな転換点となりました。
それまで曖昧だったヒグマの習性、特に「所有物への執着」や「逃げるものを追う本能」が、この事件を通じて広く知られるようになったのです。
現在、環境省や自治体が発信するクマ対策ガイドラインには、この事件から得られた教訓が多く反映されています。
「荷物を奪われたら絶対に取り返さない」「背中を見せて走って逃げない」といった鉄則は、3人の尊い犠牲の上に確立されたものと言っても過言ではありません。
まとめ:福岡大ワンゲル部 生き残り その後の真実と教訓
福岡大ワンゲル部事件は、過去の悲劇として終わらせるのではなく、私たちが安全に自然と共存するための道標とするべきです。
生き残った方々の苦悩と、亡くなった方々の無念を胸に、以下の教訓を心に刻みましょう。
野生動物への正しい知識と「撤退する勇気」の重要性
自然の中では、人間の常識は通用しません。
正しい知識を持ち、装備を整えることはもちろんですが、何よりも重要なのは「撤退する勇気」です。
天候の悪化や野生動物の出現など、少しでも不安要素があれば、目的を達成できなくても引き返す決断が必要です。
「せっかくここまで来たのだから」という思いが、命取りになることがあります。
生きて帰ることが、登山における最大の成功であることを忘れてはなりません。
事件を風化させないための語り継ぎ
事件から50年以上が経過し、当時を知る人も少なくなってきました。
しかし、ヒグマの生息域拡大や登山ブームにより、人とクマとの接触事故は近年増加傾向にあります。
この事件を「昔話」として風化させるのではなく、現在進行形のリスクに対する教訓として語り継いでいく責任が私たちにはあります。
生き残った方が長い沈黙を破って語った言葉の重みを、次世代へと繋いでいくことが大切です。
- 生き残った2名は事件後50年間、記憶を封印して生きてきた。
- サブリーダーは2020年に週刊誌の取材に応じ、当時の苦悩を告白した。
- 被害者の遺体は激しく損傷しており、死因は頸椎骨折や失血死だった。
- 加害グマは若いメスで、捕食目的ではなく排除行動で襲った可能性が高い。
- 犠牲者が残した「興梠メモ」には、絶望的な状況と故郷への思いが綴られていた。
- 荷物を取り返したことが、ヒグマの執着心を招いた最大の要因とされる。
- 当時の知識不足や正常性バイアスが、避難の遅れに繋がった。
- 福岡大学ワンダーフォーゲル部は現在も存続し、活動を続けている。
- この事件は、日本のクマ対策における重要な教訓として現代に生かされている。
- 自然の中では「撤退する勇気」こそが命を守る最大の武器となる。